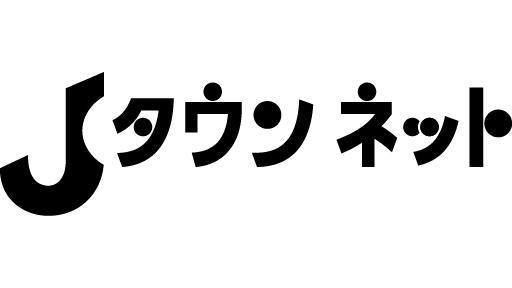日本では丸は最強の図形!?
船の名前に丸を付ける。2001年までは、船舶法の取り扱い手続きに「船舶の名称にはなるべくその末尾に丸の字を付せしむべし」と書かれていた。大きな船から小さな船まで、丸が付けられて、外国船は日本の船をマル・シップと呼んでいた。
丸には魔除けの意味があるという説がある。平安時代、「まる」は糞を意味しており、便器の「おまる」は宮中の女房言葉が伝わったものといわれる。
鬼は臭いにおいを嫌うため、子供に○○丸という名前を付けることで健やかな成長を願うともいわれている。
日本で最も知名度の高い丸は、日の丸国旗である。

円相は茶掛けの人気者
一筆で描く「円相」は茶道の世界では掛け軸としてよく使われている。
大日本茶道学会 会長(家元)の田中仙堂さんは、「円相」は 悟りや真理といった禅の心を象徴的に表現したものとされ、欠けたところがなく余ることのない様子を表していると次のように話す。
「筆の線は、その人の手の動きを、かなり忠実に反映するので、円をきれいに書くということは、かなり難しい。 途中で息切れすると、そこで、線が中断してしまう。また、大きく書くほど難しい。禅僧のみごとな大きな円相をみると、長く息を続けられる座禅を通じて形成された身体だからこそ達成できるものだと感じます。禅僧が達した禅的な境地を反映しているように思います。禅寺では、開山の座像を、飾りますが、それは、禅修行を通じて到達すべき身体の姿(坐相)を示しているようにも感じます。つまり、円相は、それを描いた禅僧が体現している身体を直接的に表現しているのです」
円相がお茶の掛け軸として人気なのは、このような深い意味を持っており、茶道の心に通じるところがあるからだろう。

村上隆も「円相」、アーティストたちの円表現
2016年3月、村上隆の個展「村上隆の五百羅漢図展」が東京の森美術館で開かれたがこのとき、東京のカイカイキキギャラリーにて村上隆による「円相」展が開かれた。
その時の案内に次のように書かれていた。
「円相は村上隆にとって、悟りを表現しているといわれる。心を無にして体の動くままに創作する瞬間を意味していると、伝統的に滑らかで熟練した筆遣いで描かれる円相において、心変わりは許されません。村上は円相を彼のユニークなやり方で、彼の作品の象徴であるお花とドクロを重ねた上にスプレーを使って表現します。円相は日本文化へのオマージュであり、複雑な芸術的および精神的歩みを経て、より自由なミニマリスト的実践へ回帰することなのです」